- 相続放棄する人は原則家の片付けはできない
- 相続放棄が認められる家の片付けの範囲を解説
- 相続放棄しても家を管理する義務だけは残る場合がある
さまざまな事情により、家族の財産を受け継がない「相続放棄」の選択をすることがあります。
相続放棄する人は、必ずしも故人と絶縁して完全に没交渉だった人とは限りません。相続しないことを決めても、故人を偲ぶ気持ちから故人が生前に住んでいた家を片付けてあげようと思う人もいるでしょう。
しかし相続放棄を決めたなら、家の片付けには注意が必要です。家の片付けをしてしまったがために相続放棄が認められない可能性があるからです。
今回は相続放棄と家の片付けとの関係について解説します。
目次
相続放棄とは

故人の財産は、法定相続人が法律で定められた順番に受け継ぐ権利があります。
しかし故人(被相続人)の財産を受け継ぎたくない法定相続人は、順番が来ても財産をもらわないことができます。これを相続放棄と呼びます。
法定相続の順番や、自分より順位が上の人が相続放棄したときにはどこまで順位が繰り下がるのかについては以下の記事でも詳しく解説しています。
 相続放棄のリレーはどこまで続くか|相続順位と範囲・最終的な行先を解説
相続放棄のリレーはどこまで続くか|相続順位と範囲・最終的な行先を解説
なお法定相続順位が下の人や、あるいは法定相続人以外の人でも、被相続人が遺言書で自分を相続人に指定していたときには相続人になります。
「自分は関係ない」と思わず、相続放棄を検討する可能性は誰にでもあると認識しておきましょう。
相続放棄の手続きの仕方
相続放棄は、自分が相続人である事実を知った日から3ヶ月以内に行います。
申述先は故人が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。相続放棄のための方法については以下の記事を参考にしてください。
 相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ
相続放棄したいなら家の片付けに注意が必要

最初に申し上げたとおり、相続放棄を決めたなら故人の家の片付けには注意が必要です。
相続放棄する人は、被相続人の財産を勝手に処分してはいけません。
家を片付けて被相続人の荷物を処分してしまうと、その人は被相続人の財産をプラスもマイナスもまとめて限度なく受け継ぐ(単純承認)意思があるとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」と呼びます。
第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
上記で引用した第921条3項でもわかるとおり、相続放棄の申述をした後でも単純承認とみなされる可能性があります。相続放棄の手続きが済んだから家を片付けても大丈夫、とはなりませんのでご注意ください。
故人の家を片付けて、すっきりした気持ちで故人を送りだしてあげようとする優しい気持ち故の行動であっても、それが後悔の元になる可能性があります。基本的に相続放棄を決めた人は故人の遺品には手をつけない方が賢明です。
家の売却・賃貸解約も片付けと同様
「家の片付け」と聞くと、住宅の中にある家具や家電、衣類や日用品などの片付けを連想しますが、住宅そのものも同様です。
不動産はもちろん財産として扱われます。そのため故人が住んでいた土地建物が故人の所有だったときには相続放棄する人が勝手に売却等をしてはいけないという点については、多くの人も予想がつくでしょう。
しかし、ついうっかり行ってしまいそうな行為が、故人が住んでいたアパートやマンションの賃貸契約を解約する行為です。
建物の賃貸借契約においては、借主が死亡したときの賃貸借契約はそのまま相続人に引き継がれます。つまり賃貸借契約を解約した人は、自らが相続人であると認めたことになります。そのため相続の意思があるとみなされ相続放棄ができなくなってしまうのです。
家の片づけ以外に相続放棄が無効の理由

相続放棄したいと思っても認められなくなる理由は、家の片付けだけではありません。
上記で説明した「法定単純承認」だけでも、家の片付け以外にもいろいろとあります。例えば故人の死後に住宅へ郵送された光熱費の請求書を代わりに支払うだけでも法定単純承認とみなされてしまいます。
法定単純承認の他の事例や、法定単純承認以外に相続放棄が認められない理由については以下の記事をご確認ください。
 相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ
相続放棄が認められる家の片付けの範囲

相続放棄する人は家の片付けをしない方が良いとは知っていても、故人の家をそのままにしておくのは気が引けるという人もいるでしょう。
自宅で突然に亡くなった人の場合には食材や調理済みの食品などがそのままになっている可能性もあるため、放置しておくと悪臭や害虫が発生して近隣に迷惑をかけてしまうかもしれません。
相続放棄する人・すでに相続放棄した人であっても、一定の範囲内であれば家の片付けができます。
以下からは家を片付けても相続放棄が認められる範囲を説明します。
整理整頓
相続放棄が認められなくなる「片付け」とは、モノを処分する行為です。
モノを動かしたりまとめたりして整理整頓する「片付け」は、そのモノが家の中からなくなることがないため財産の処分にはあたりません。
掃除・メンテナンス(保全目的)
整理整頓と同様、家の掃除をしても財産を処分したとはみなされません。掃除機をかけたり溜まっている食器・鍋を洗ったりする行為も問題ありません。
また家のメンテナンスも、そのメンテナンスが住宅の保全目的である場合には問題ありません。
《保全目的のメンテナンスの例》
- 草むしり
- 割れた窓ガラスの修繕
- 瓦・外壁・雨どいの修理・交換
- 網戸の貼り換え
- シロアリ駆除 他
美観や機能を高めるためのメンテナンスは含まれませんのでご注意ください。
ゴミ・生鮮食品の処分
明らかに資産価値がないゴミに関しては、処分しても相続放棄への影響はありません。
また肉や魚・野菜などの生鮮食品に関しても、そのまま放置しておけば価値のないゴミに変わることが明らかなため処分できます。
ただし価値があるかどうかの判断は人により異なります。価値がないと思われた趣味の品などが、収集家やマニアにとっては垂涎の品になるかもしれません。
うっかり金銭的価値があるモノを処分しないよう、できるだけすべてのモノは片付けずに残しておくことをおすすめします。
写真など思い出の品の引き取り
第三者にとっては価値がないモノでも、自分にとっては思い入れがあるモノが故人の家に残されている可能性もあります。
その思い出の品が、誰から見ても明らかに資産価値がないモノであれば、ゴミの処分と同様に引き取りをしても構いません。
《思い出の品の例》
- 写真
- 手紙・ハガキ(資産に関係する内容が書かれていないもの)
- 古着(売却しても利益にならないもの)
- 位牌 他
逆に、以下のような思い出の品を形見分けとして引き取ると財産処分とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があるためご注意ください。
《財産処分とみなされる恐れがある思い出の品の例》
- 貴金属・アクセサリー
- 絵画・骨董品
- ブランド品
- 楽器
- 希少本
- 趣味のグッズ 他
相続財産の調査・仕分け
相続人に指定された人は、相続するか相続放棄するかを決定する前に、被相続人の相続財産の調査をすることが認められています。
相続財産の調査をするために被相続人の家を片付け、住宅に残されていた書類等を持ち帰ったとしても、財産の処分とはみなされません。なぜなら財産の精査をしなければ相続放棄の検討すらできないからです。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
ただし持ち帰った書類やモノを換金したり、不要と自己判断して廃棄すると財産の処分に該当します。
また書類等を勝手に持ち帰ると、たとえそれが調査のためであっても財産を隠蔽したと思われる恐れがありますので、事前に専門家への相談をおすすめします。
相続放棄しても家の片付け義務が残る人
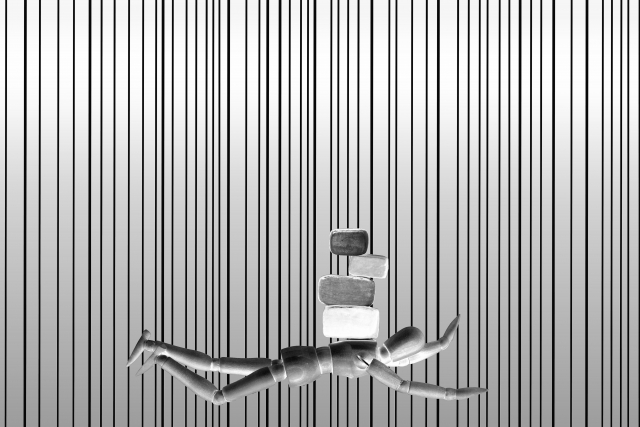
ここまでの説明を読んで「財産処分とみなされないように家の片付けは一切しない」と心に決めた人がいるかもしれません。
しかし相続放棄する・しないに関わらず、故人の家の片付けをせざるを得ない人もいます。
以下からは相続放棄しても家の片付け義務がある人の例を3つご紹介します。
故人と同居していた妻・夫
故人と生前まで同居していた妻もしくは夫は、相続放棄しても家の管理責任が残ります。
子などの次の相続人がその家を相続するまで、家の価値が目減りしないように保全させなければいけません。
原則として被相続人が住んでいた家の光熱費支払をすると相続放棄が認められなくなりますが、同居していた夫婦の場合は別です。
家賃や公共料金などの日常生活にともない発生した費用は配偶者にも「日常家事債務の連帯責任」があると定められているため、妻もしくは夫自身の財産から支払う必要があります。
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
賃貸契約の連帯保証人になっていた人
故人が生前にパートやマンションの賃貸契約をした際、連帯保証人に名を連ねていた人は相続放棄の有無に関わらず解約時の原状回復義務があります。
連帯保証人は故人と同等の契約義務があるため、相続放棄しても契約義務が残るからです。
ただし原状回復工事のために家を片付け、家の中にあった家財道具を処分すると、こちらは財産処分として扱われます。家財道具は売却・廃棄等をせずにトランクルームなどに保管しておいた方が望ましいでしょう。
孤独死現場・ゴミ屋敷
被相続人が孤独死したために住宅が汚染されたり、遺された家がゴミ屋敷であったとしても、本来相続放棄する人には片付けする義務はありません。
しかし孤独死の現場やゴミ屋敷の放置は衛生環境が悪化しますし、故人と関係が深い人であったら道義的にも放置はなかなかできないものです。
そのような場合には相続放棄する人自身が特殊清掃の費用を出し、業者に依頼しても相続放棄への影響は薄いと考えられます。そのような現場は家財道具も汚染されている可能性が高いので、売却しても値が付かないことも考えられます。
孤独死やゴミ屋敷の汚染度合いは状況によって異なるため、判断に困るときには信頼のおける業者と相談するか、専門家の指示を仰いでください。
相続放棄後の家の管理は相続財産管理人に

相続放棄すると、相続の権利は次の相続人に移ります。
しかし他に相続する人がいない場合には、自分が相続放棄した後に家などの財産を管理する人間が必要です。
家庭裁判所で相続財産管理人を立てれば、全員が相続放棄した後の財産管理を行ってもらえます。相続財産管理人には相続権のない親族などもなれますが、弁護士などに依頼するのが一般的です。
故人の負の遺産を相続しないためにも、きちんと相続財産管理人を立てて手離れさせましょう。
まとめ
今回は相続放棄するときに注意しておきたい家の片付けについて解説しました。
親切心から行った家の片付けが、いらぬトラブルの原因になるかもしれません。必要に応じて弁護士などの専門家の助けを借りつつ、確実に相続放棄できるように対策しましょう。
 相続放棄申述書とは|相続放棄に必要な手続きの流れと費用
相続放棄申述書とは|相続放棄に必要な手続きの流れと費用
 ライター紹介 | 杉田 Sugita
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。
受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。
▶︎今すぐ無料ダウンロード!



