- 新聞には紙新聞と電子版新聞の2種類がある
- 電子版新聞のメリットは「場所を選ばない」「過去記事が検索できる」他
- 電子版新聞のデメリットは「一覧性がない」「新たな出会いがない」他
- 発行部数が多い日本の主要新聞5紙の電子版を比較
「新聞」には、紙で読む新聞と、パソコンやスマートフォンなどで見る電子版新聞の2種類があります。
今回は新聞を電子版で読むメリット・デメリットを説明し、発行部数の多い主要新聞5紙の電子版新聞を比較しながらご紹介します。
目次
電子版新聞の利用者は増加傾向にある
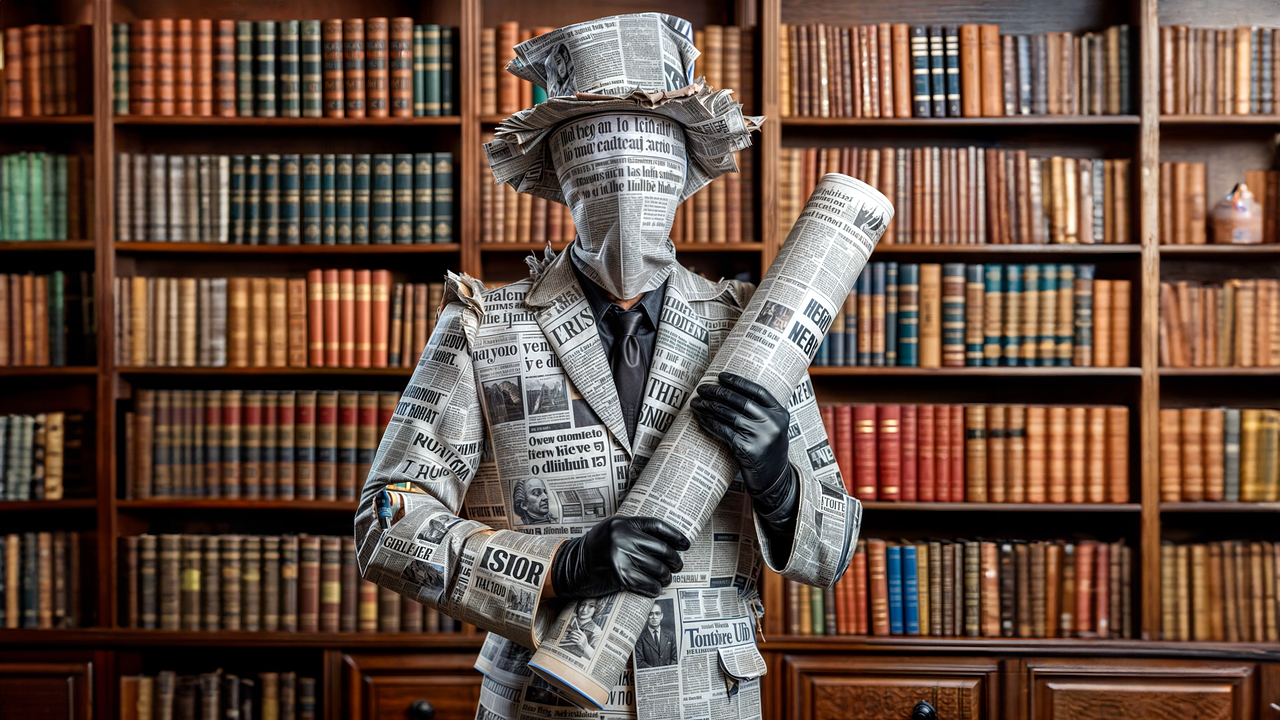
紙の新聞に対して電子版の新聞が普及率がまだ低いものの、20代~50代を中心に少しずつ普及が進んでいます。
最近では紙の新聞を止めた世帯が増えているため、新聞社が発行部数の減少を補うために電子版を積極的に進めています。特に日経新聞はデジタル化を推し進め、2025年1月に公表した日経新聞の紙新聞・電子版新聞の購読者数はほぼ半々という結果になりました。
参考 日経朝刊・電子版の購読数 235万日本経済新聞他の新聞社も今後ますますデジタルシフトを進めていくと考えられ、将来は紙の新聞よりも電子版の購読数の方が多いという未来が来るかもしれません。
紙新聞の利用者数減少については、以下の記事で詳しくまとめています。
新聞を電子版で読むメリット

新聞を紙でなく電子版で読むと、以下のようなメリットが生まれると考えられます。
いつでもどこでも読める
日本新聞協会の調査によると、紙の新聞を読む人の84.2%は自宅内で読んでいるそうです。次に多い場所が職場や学校で11.5%となり、移動中や外出先で新聞を読む人はほとんどいません。
対して電子版は自宅だけでなく職場や学校、通勤通学の移動中など、多くの場所で読まれています。スマートフォンがあればいつでもどこでも新聞を読めるため、最新のニュースを見逃す心配がありません。
参考 電子版と紙の新聞の比較新聞広告データアーカイブ過去記事の検索ができる
紙の新聞は古紙回収で処分してしまうと、もう読むことはできません。すべての紙新聞を保管すると場所ふさぎになり、記事をスクラップするのは手間がかかります。
電子版であれば、後で読み返したい記事があるときには検索して読み返すことができます。
ほとんどの電子版新聞では検索機能が搭載されています。ただし新聞社によって検索できる期間や機能、記事の種類は異なりますのでご注意ください。
古紙回収・ゴミ出しが不要
1紙だけならさして重くない新聞紙も、1週間分、1か月分が溜まると処分が大変です。
高齢者のみの世帯だと、新聞紙を紐でまとめてゴミ集積所に運ぶのも苦労します。電子版であればゴミ出しはいっさい不要です。
資源の節約・地球環境の保護につながる
紙新聞から電子版新聞に移行することは、資源の節約や環境保護につながります。
日本で発行されている新聞は回収された新聞古紙を主な原料として作られていますが、配送やリサイクルの過程でCO2の排出は避けられません。
SDGsの観点からも、電子版の利用は推奨されています。
新聞を電子版で読むデメリット

新聞を電子版で読むメリットを理解したら、その次はデメリットについても理解しておきましょう。
新聞を電子版で読むことには、以下のようなデメリットがあると考えられます。
一覧性がない
一覧性(いちらんせい)とは、ひとめで全体の内容がわかるようにまとめられていることです。
紙の新聞を手に取ったときには、まず一面の見出しとリード文でトップニュースの内容がざっと把握できます。関連記事が二面、三面にある場合も一覧性があるため、スムーズに内容が理解できるように作られています。
電子版の新聞ではすべての文字が基本的に同サイズであり、見出しについても紙新聞ほどのインパクトは与えられないため、一覧性には欠けてしまいます。
自分が興味関心がある情報しか出会えない
インターネットで得られる情報は、基本的には自分が能動的に探した情報となります。
ニュースサイトやポータルサイトを見ても、最近ではユーザーの趣味嗜好に合わせた情報を優先的に表示するパーソナライズ化が進んでいるため、利用者は自分の興味関心がある情報ばかりを目にすることになり、それ以外の情報に触れる機会が減少する「フィルタリングバブル」が発生する傾向にあります。
心身に悪影響を与える恐れがある
新聞の電子版はパソコンやスマートフォン、タブレット等のデジタル端末から閲覧します。
しかしデジタル端末の使い過ぎには注意が必要です。パソコンやスマートフォン等を長く見続けることにより、以下のような心身への悪影響があると考えられます。
ただし以下の現象は、あくまでもスマートフォン等を使い過ぎたときに考えられる心身への悪影響です。時間制限を設ける、適度に休憩をはさんで目を休ませる、正しい姿勢で閲覧する、寝る前には読まないなどの適切な対策をとればそこまで心配する必要はありません。
| 目への悪影響 | 眼精疲労・ドライアイ・スマホ老眼・視力低下など |
| 睡眠への悪影響 | ブルーライトによる睡眠の質の低下・不眠など |
| 肩・首への悪影響 | 肩こり・首こり・ストレートネック・猫背など |
| 脳への悪影響 | 脳疲労・自律神経の乱れ・認知症など |
| 精神的な悪影響 | スマホ依存症・集中力や記憶力の低下・ストレスなど |
大手新聞5紙の電子版を徹底比較
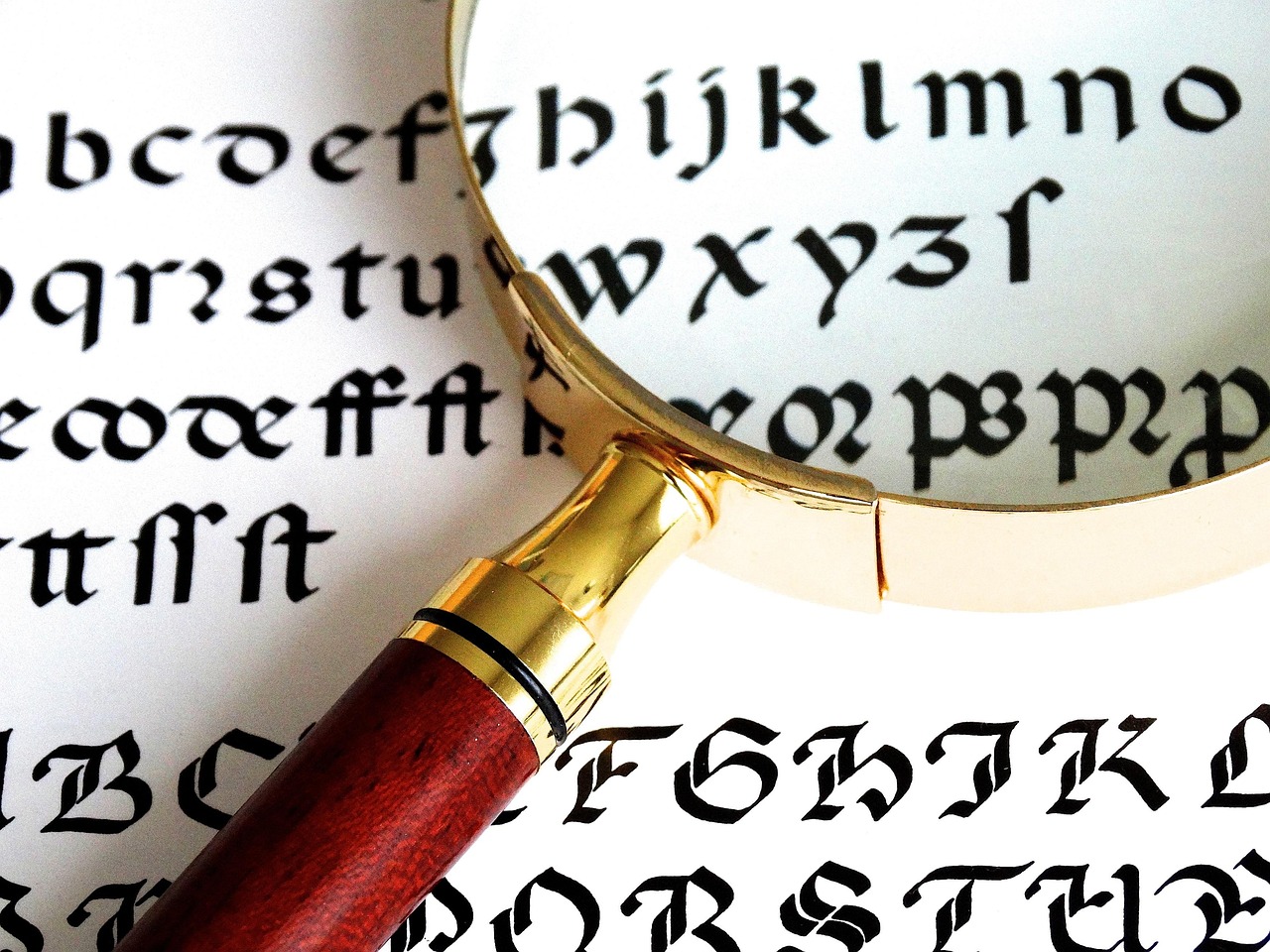
以下からは具体的に、新聞ごとの電子版を比較していきましょう。
より多くの人の参考になるように、今回は新聞・雑誌・専門紙誌・フリーペーパーの部数を公正な立場から公査(監査)・認証する日本ABC協会が公表している新聞の発行部数ランキング順に、大手新聞5紙の電子版をご紹介します。
1位:読売新聞
読売新聞オンラインは、日本でもっとも発行部数が多い読売新聞の電子版です。宅配新聞の購読者は追加料金なしですべての機能が利用でき、読売新聞と契約していない人でも掲載記事は無料で閲覧できます。
| 電子版の名称 | 読売新聞オンライン |
| 電子版の月額費用(税込) | 宅配購読者:無料 電子版のみ:無料(サービス制限あり) |
| 電子版独自コンテンツ | あり |
| 紙面ビューアー機能 | あり |
| 音声読み上げ機能 | あり(注目ニュースのみ) |
| 検索機能 | あり |
| 記事保存・スクラップ機能 | あり |
2位:朝日新聞
朝日新聞デジタルは、無料のニュースサイトと有料の電子版で構成されたオンラインサイトです。前身のasahi.comは日本のインターネット黎明期から存在しており、電子版の新聞としてはもっとも老舗です。
| 電子版の名称 | 朝日新聞デジタル |
| 電子版の月額費用(税込) | 宅配購読者:500~1,000円 電子版のみ:980~3,800円 |
| 電子版独自コンテンツ | あり |
| 紙面ビューアー機能 | あり |
| 音声読み上げ機能 | あり |
| 検索機能 | あり |
| 記事保存・スクラップ機能 | あり |
3位:毎日新聞
毎日新聞デジタルは、読売新聞、朝日新聞とともに三大全国紙のひとつに数えられている毎日新聞社が提供する電子版です。英語版「The Mainichi」もあります。
| 電子版の名称 | 毎日新聞デジタル |
| 電子版の月額費用(税込) | 宅配購読者:無料~1,078円 電子版のみ:980~3,200円 |
| 電子版独自コンテンツ | あり |
| 紙面ビューアー機能 | あり(プレミアムプランのみ) |
| 音声読み上げ機能 | あり |
| 検索機能 | あり(プレミアムプランのみ) |
| 記事保存・スクラップ機能 | あり |
4位:日本経済新聞
日本経済新聞は日本で唯一の経済専門新聞です。経済ニュースが充実し、特に電子版は就活生の情報収集などにも役立てられています。
| 電子版の名称 | 日経電子版 |
| 電子版の月額費用(税込) | 宅配購読者:1,000~2,500円 電子版のみ:4,277円 |
| 電子版独自コンテンツ | あり |
| 紙面ビューアー機能 | あり |
| 音声読み上げ機能 | あり |
| 検索機能 | あり |
| 記事保存・スクラップ機能 | あり |
5位:産経新聞
産経新聞の正式名称は「産業経済新聞」と言いますが、日本経済新聞のような経済紙ではなく一般新聞です。
電子版の契約により数独パズルなどの独自コンテンツ利用、プレゼント応募や電子版会員向けイベントへの参加申し込みができます。
| 電子版の名称 | 産経ニュース |
| 電子版の月額費用(税込) | 宅配購読者:無料~2,750円 電子版のみ:無料~2,750円 |
| 電子版独自コンテンツ | あり |
| 紙面ビューアー機能 | あり(有料プランのみ) |
| 音声読み上げ機能 | なし |
| 検索機能 | あり(有料プランのみ) |
| 記事保存・スクラップ機能 | あり(有料プランのみ) |
まとめ

今回は新聞電子版のメリットとデメリットを説明し、主要新聞5紙の電子版をご紹介しました。
これからも、ますます新聞電子版の普及は進んでいくと考えられます。契約している紙の新聞をそろそろ止めようと思っている人は、購読停止ではなく新聞電子版への変更も検討してみてはいかがでしょうか。
 ライター紹介 | 杉田 Sugita
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。
受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。
▶︎今すぐ無料ダウンロード!



