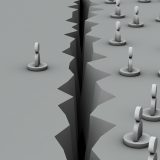- 絶縁状の作成・送付は弁護士に依頼できる
- 弁護士が絶縁状を送付すると自分の居場所が知られないなどのメリットがある
- 絶縁状の作成・送付を弁護士に依頼するときの費用は最低10万円が目安
「絶縁」は自分一人の気持ちで決められますが、絶縁しようとしている相手の気持ちはどうだかわかりません。
不仲な相手、または相手から見れば良好な関係だと思っていた相手から絶縁状を叩きつけられることによって、相手が何らかの反応を返してくることは十分に考えられます。
自分は「もう絶縁した相手だから関係ない」と考えていても相手にとってはそうではなく、状況によっては大きなトラブルや事件になる危険性が発生してしまうかもしれません。
トラブルを最小限に抑えて相手とスムーズに絶縁を果たすためにはどうしたら良いでしょうか。
今回は第三者と絶縁するときの味方となり得る弁護士の存在について解説します。
目次
第三者と関係が悪化する可能性は誰でもある

「絶縁」は当然のことながら、絶縁する対象の人が存在します。
それは家族であっても変わりません。子供の頃に仲が良かった親や兄弟姉妹でも、大人になってそれぞれの事情が変化して関係が悪化する可能性があります。
家族との関係性を終了させる行為は「墓じまい」や「年賀状じまい」になぞらえて「家族じまい」とも呼ばれています。
家族じまいをしたくなる理由や、家族との絶縁による影響について知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
「絶縁」には法的な拘束力がない

今回は第三者とスムーズに絶縁する方法について解説しますが、まずは「絶縁」には法的な拘束力がないことを理解しておきましょう。
絶縁した相手からの連絡を遮断するためには、警察や裁判所からの接近禁止命令が必要になります。ストーカー行為や何らかの危険に直面している人でない限り、接近禁止命令はそうそう発令されるものではありません。
家族と絶縁しても残る義務と権利がある
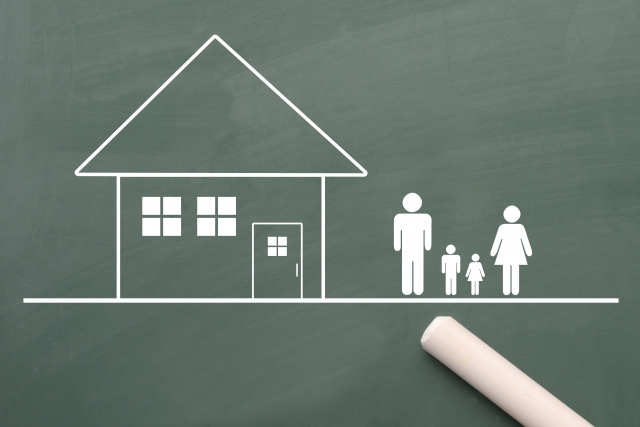
絶縁する相手が家族の場合には、絶縁した後でも以下の義務・権利は引き続き発生します。
扶養義務
扶養義務とは、自分の収入や資産だけでは生活していけない親族を経済的に援助する義務のことです。主な扶養義務者は直系血族(祖父母・父母・子)および兄弟姉妹です。
扶養義務者による扶養は生活保護よりも優先されるため、経済的に困窮した親族が生活保護の申請をしたときには扶養義務者にあたる人に連絡が入ります。
相互扶助義務
相互扶助義務とは、夫婦がお互い助け合って同じレベルで生活できるように協力する義務のことです。法的に婚姻した夫婦には以下4つの義務が互いに生じます。
- 同居義務
- 協力義務
- 扶助義務
- 貞操義務
配偶者に対して絶縁宣言したとしても、夫婦には上記4つの義務があるため、絶縁した側が有責者となって離婚に際して不利に働きます。
相続権
絶縁した相手が自分と法定相続の関係にある場合、お互いが生きている間には関係を断ち切ったとしても、自分または絶縁した相手が亡くなったときの相続には影響しません。
法定相続の範囲は配偶者および血族(子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹・甥・姪)です。相続順位など詳しくは以下の記事でご確認ください。
自分の財産を絶縁した家族に渡さないよう遺言しておいたとしても、法定相続人にあたる人には遺留分の請求権があるため、相手が権利を行使したら一定の財産は相続させる必要があります。
遺留分については以下の記事で詳しく解説しています。
絶縁状は相手に決別の意思を伝える手段

絶縁までしようと考えるのですから、対象となる相手にはこれまで積もりに積もった深い恨みがあると推察できます。
いくら法的には効力がないとはいえ、絶縁しようとする相手に何も言わずにフェードアウトするだけでは気持ちの収まりがつかないという人もいらっしゃるでしょう。
自分の気持ちに区切りをつけるため、そして絶縁する相手に自分の気持ちを明確に伝えてから決別する手段として、絶縁状の送付という方法も一案です。
また絶縁状を送ることで、しつこくつきまとってくる相手につきまとい行為をやめるように けん制することも可能です。
以下の記事では絶縁する相手ごとの絶縁状の書き方を解説しています。本記事とあわせて参考にしてください。
絶縁状の送付には弁護士が後ろ盾になれる
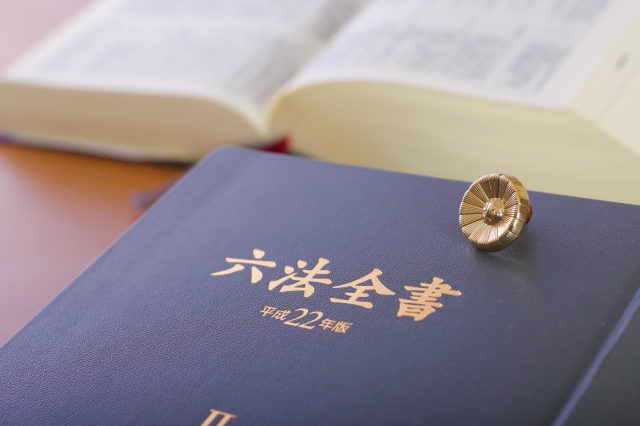
絶縁状を絶縁する相手に送るときには、弁護士の助けを借りるとより効力がアップするかもしれません。
弁護士は法律に関するプロですが、交渉事のプロでもあります。
確かに「絶縁」には法的な効力はありませんが、絶縁状の作成を弁護士に手伝ってもらったり、絶縁する相手への送付を弁護士経由で行うことで、弁護士が自分の「絶縁したい」という意思の後ろ盾になってくれます。
絶縁状の作成・送付を弁護士に依頼するメリット

絶縁状の作成や送付を弁護士に依頼すると、以下4つのメリットが発生します。
1.相手にプレッシャーをかけられる
多くの人にとって、弁護士は権威の象徴です。
弁護士事務所から絶縁状を送ることで、相手に自分の本気度を知らしめることができ、絶縁される相手は強いプレッシャーを感じることでしょう。
学歴や収入で人間の優劣を決めるタイプの相手にはさらに効果的です。
2.自分の居場所を知られずにすむ
弁護士事務所が絶縁状の作成に関わった場合には、できあがった絶縁状は弁護士事務所の名義で郵送されることがほとんどです。
暴力や過干渉等の理由により絶縁する相手に自分の居場所を知られたくないときでも、弁護士事務所が郵送元になってくれていれば住所等が相手に知られる心配がありません。
3.交渉窓口になってくれる
絶縁する相手の顔を見るだけ、声を聞くだけで苦痛に感じてしまい、今後いっさい連絡を取りたくない場合には、相手がこちらの連絡するときの窓口を弁護士に指定することで直接のやりとりが避けられます。
また絶縁予定の相手から過去に肉体的・精神的・経済的な苦痛や損害を与えられており、絶縁を機に慰謝料や損害賠償などの請求をしたいときでも、弁護士が代理人として交渉事にあたってくれます。
4.法律や社会常識に逸脱しない絶縁状が作れる
絶縁という状況に気が高ぶってしまい、自分の思いのたけをそのまま絶縁状にぶつけてしまうと、かえって自分の不利になってしまうかもしれません。
脅迫や名誉棄損とも取られる文章を絶縁状に書くことは厳禁です。もし法律や社会常識から逸脱した内容の文章を書くと、相手から逆に訴えられたり、警察に被害届を出される危険性があります。
弁護士のアドバイスを受けながら絶縁状を作成すれば、感情的になりすぎない適切な内容の絶縁状が作成できます。
また弁護士に相談することで、絶縁したい相手だけでなく関係してくる第三者との今後についても法的な観点からのアドバイスが受けられる可能性があります。
絶縁状の作成を弁護士に依頼するデメリット

絶縁状の作成を弁護士に頼むメリットを確認した後は、反対にデメリットについても確認しておきましょう。
費用がかかる
自分で作成した絶縁状を送るだけなら費用はほぼ郵便切手代のみですが、弁護士に作成の支援をしてもらったときには費用が発生します。
経済的な余裕がない人の場合、自分で作れば数百円程度ですむ書類に高額な費用をかけることにはためらいを感じてしまうかもしれません。
絶縁状の作成を弁護士に依頼するときの費用については以下で説明します。
依頼を受けるかは弁護士次第
弁護士は、依頼があれば何でもかんでも引き受けるとは限りません。
依頼を受けるかは弁護士次第です。絶縁状のように法的効力がないことが明らかな書類は作成しても無意味だと敬遠する弁護士も存在します。
絶縁状の作成支援を引き受けるか否かは、それぞれの弁護士の考え方や専門分野、経営理念により異なります。もし相談した弁護士から依頼を引き受けられないと断られた場合には、依頼を引き受けてくれる弁護士が見つかるまであきらめずに探すことをおすすめします。
絶縁状の送付を弁護士に依頼する費用

弁護士に絶縁状の作成と送付をお願いするときの費用は、一般的に3~10万円です。
ですが着手金の最低金額を10万円に設定している弁護士事務所が多いので、最低10万円はかかると考えておいた方が良いでしょう。
絶縁状を送るだけでなく慰謝料や損害賠償請求なども行ったり、送付後の相手方との交渉まで依頼した場合には別途費用が発生します。絶縁の状況や自分の希望により費用は異なるため、必ず依頼前に詳細な費用を確認してください。
以下の記事では相続における弁護士費用を解説しています。絶縁状に関する費用としても一定の参考になるため、あわせて熟読をおすすめします。
絶縁状を送るだけなら行政書士の利用も一案

できるだけ費用を抑えつつ、なおかつ専門家の助けも借りて絶縁状を作成したい人には、弁護士ではなく行政書士の利用もおすすめできます。
行政書士は弁護士と同じように、法的に問題ない文書の作成および送付を代行してくれます。費用は5千~1万円程度が目安となりますので弁護士に依頼するよりも安価です。
ただし行政書士は、絶縁状を郵送した後の相手との交渉窓口にはなってくれませんのでご注意ください。
まとめ
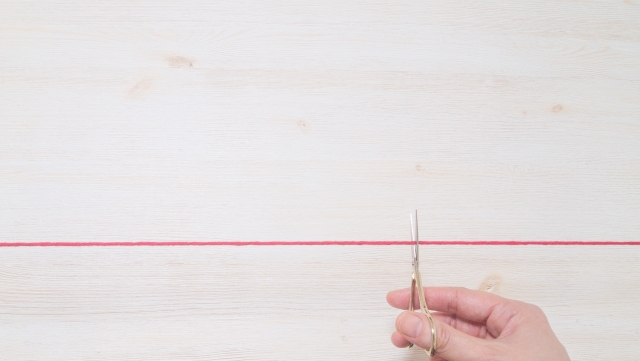
今回は絶縁状の作成や送付を手伝ってくれる弁護士について解説しました。
「絶縁」は自分と相手の人生を左右するかもしれない重要な決断です。絶縁状の送付により大きなトラブルを招かないよう、専門家の力を借りてとどこおりなく事を進められるようにしましょう。
 ライター紹介 | 杉田 Sugita
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。
受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。
▶︎今すぐ無料ダウンロード!