- 有価証券(株式など)は相続の対象
- 株を相続したときには名義変更が必要
- 上場株の名義変更のやりかたを解説
- 相続財産に非上場株があったときには専門家に相談がおすすめ
2014年度から始まったNISA(少額投資非課税制度)の普及に伴い、近年では多くの人が投資に参加するようになりました。
年代や性別を問わず、最近では「株をやっている人」が少なくありません。特にシニア層では老後の不安を解消するために、積極的に資産運用を始める人が増えています。
投資をしていた人が亡くなったときには、その人が保有していた株は相続の対象となります。財産が現金の場合にはそのまま受け取れば良いですが、財産が株式だった場合にはどうしたら良いでしょうか。
今回は株の名義変更をするやりかたについて解説します。家族が投資をしている人は参考にしてください。
目次
株は相続財産の一種

人が亡くなったときに相続財産に見なされるものは、現金や不動産だけではありません。亡くなった人(被相続人)の所有物のうち、金銭に見積もることのできるものはすべて相続財産に含まれます。
具体的には以下のモノや権利が相続財産となります。
- 現金および預貯金
- 有価証券(株式・債券・ゴルフ会員権など)
- 不動産(土地・建物)
- 不動産上の権利(借地権・借家権・抵当権など)
- 動産(自動車・貴金属・骨董品など)
- 知的財産権(著作権など)
- 損害賠償請求権
- 生命保険金(受取人が被相続人のもの)
- その他(中古買取金額が目安として5万円以上となるもの)
上記でも確認できるように確認できるように、株は相続財産の一種です。
株を相続したときは名義変更が必要

株を保有していた人が亡くなり、相続手続きが完了するまでは、株はすべての相続人が準共有(物質でないものを複数人で共有する)状態となります。
相続手続きが終了すれば株の保有権利は相続が決定した相続人のものになりますが、名義変更をしないと株主権は被相続人のまま変わりません。
株保有者の死去により株が相続された事実が発行会社では把握できないため、相続した株を本当に自分のものにするためには名義変更の手続きが必要なのです。
株を名義変更しないと起こり得るリスク

相続した株をいつまでも名義変更しないままでいると、どんな問題が起きてしまうのでしょうか。
以下からは相続した株の名義を変更しなかったときに起こり得るリスクを4つ説明します。
配当金や株主優待が受け取れない
名義変更をしないと、株の発行会社が管理している株主名簿が更新されません。
株主に対する配当金や株主優待は株主名簿に記載された人物へ与えられるため、名義変更していない相続人は配当金および株主優待を受け取れなくなります。
相続手続きの途中で権利確定した配当金・株主優待は手続きが終了した後に受け取れますが、発行会社ごとに3~5年の期限が設けられています。期限を過ぎた権利は消滅し、請求しても受け取ることができません。
議決権が行使できない
議決権(ぎけつけん)とは、株主が株主総会で議案に賛否を表明する権利のことです。議決権を行使することで、発行会社の取締役の選任や解任など会社の経営に影響を与えることができます。
しかし名義変更がされていない株を持っていても、正当な株主とは認められません。もし保有株の発行会社に対して要求があったとしても、議決権の行使どころか、株主総会の参加すらできなくなります。
相続税の延滞税・無申告加算税がかかる可能性
相続税の申告は、相続によって財産を得たひとりひとりが各々に行わなければいけません。
名義変更していない状態でも相続税の申告はできますが、相続後に名義変更を怠っているような人は、相続税の申告に対しても無頓着でいる可能性が否定できません。
相続税は被相続人が亡くなった日から10ケ月が納付期限です。もし期限を過ぎても相続税の申告や納付がされないままだと、延滞税や無申告加算税、または過少申告加算税などのペナルティが発生します。
さらに相続税の未申告がうっかりミスではなく悪質な脱税行為であると判断された場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。
株の権利が消滅する
株式発行会社が株主宛に送る通知書などの書類は、株主名簿に記載の人物が亡くなっているときには「宛先不明」として各会社に戻ってしまいます。
この状態が5年間続き、配当金の受領もされていないことが確認できたときには、対象の人物は「所在不明株主」として扱われます。
株式発行会社は所在不明株主が持っていた株を、取締役会の決議後に一定の手続きを踏めば売却や自社による買い取りをしても良いと認められています。
取締役会の決議がされた後は、名義変更されてない株の権利は消滅します。売却代金はその後10年間は発行会社に支払い請求できますが、株の権利を取り戻すことはできません。
相続した株を名義変更する方法
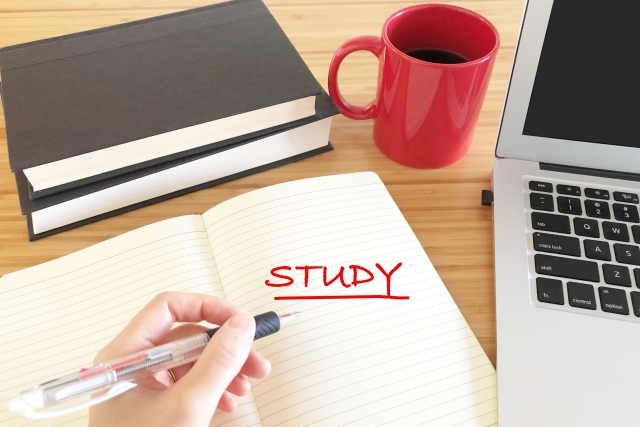
それでは、実際に株の名義変更をするときの手続きのしかたについて確認しましょう。
今回は株式を相続により受け取った場合の手続きについて説明します。贈与やその他の理由により名義変更する場合には必要書類などが異なりますのでご注意ください、
名義変更の流れ
亡くなった人の財産に株式が含まれているときには、まず対象の株式の評価額を算出して、算出された金額をもとに相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはいけません。
具体的な流れは以下の記事で詳しく解説しています。今回の記事とあわせて参考にしてください。
申請先
名義変更の申請は、被相続人が証券口座を開いていた証券会社に対して行います。
相続人が株の発行会社に対して連絡をする必要はありません。株の発行会社への連絡は申請先の証券会社が株主の代わりに行ってくれます。
被相続人がどこの証券会社で口座を開いていたかがわからないときには「ほふり(証券保険振替機構/JASDEC)」に問い合わせれば調べてもらえます。
ほふりの調査には1~2ケ月程度の時間を要しますので、被相続人が生前に株の保有について言及していた記憶がある人は早めに問い合わせることをおすすめします。
参考 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合証券保険振替機構必要書類
「株を相続したので名義変更をしたい」と各証券会社に連絡すると、手続きの流れや必要書類、書類の記入例などを記載した資料一式が送られてきます。
証券会社や株の発行会社により多少の違いはありますが、相続による名義変更の際に必要となる書類は一般的に以下のとおりです。
- 申請書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議をした場合)
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
- 検認調書または検認済み証明書の写し(遺言書がある場合)
申請手続きを相続人ではなく弁護士等の第三者が行う場合には、別途委任状なども必要になります。
費用
株の名義変更にかかる費用は証券会社ごとに異なります。また、保有している株銘柄の件数や単元数、名義変更した株をどこの証券会社の口座に移管するかでも金額が異なってきます。
一部の証券会社では、相続による名義変更の場合には名義変更の手数料を無料にしているところも存在します。ただし、その場合でも残高証明書を発行する費用他は発生しますのでご注意ください。
期限
株の名義変更自体には、特に法的な期限は設けられていません。
ですが上記でも説明したように、株の名義変更をしないと株式保有の権利や配当金、相続税申告などに影響があります。
期限がないからいつでも良いとばかりに名義変更手続きを放置しておくと、さまざまな支障が生じてきますので、できるだけ早めに手続きを開始するようにしてください。
名義変更時には受取人の証券口座が必要

ここまで株の名義変更について説明をしてきましたが、中には「証券口座の名義変更をする」つもりで読んでいる人もいらっしゃるかもしれません。
実際には、証券口座の名義変更はできません。相続による名義変更の申請を受けた証券会社は、被相続人の証券口座で保有されている「株」の名義変更を行い、相続人の証券口座に移す手続きを取るのです。
そのため株の名義変更をするときには、株の移行先となる新たな証券口座が必要となります。相続人が証券口座を持っていない場合には口座開設が必要です。
相続人の証券口座は、必ずしも被相続人の証券口座と同じ証券会社である必要はありません。すでに証券口座をお持ちであれば、既存の口座に移行すると申請書に記すだけで大丈夫です。
名義変更が終わった証券口座はカラ口座となり、閉鎖手続きが行われます。証券会社によっては自動的に閉鎖となるところもありますが、別途相続人による閉鎖申請を求められる場合もありますので、名義変更を行う証券会社にお問い合わせください。
相続した株式が非上場会社の場合

本記事のご説明は、証券会社で取り扱っている上場会社の株の名義変更に関するご説明です。
上場していない非上場会社の場合には、証券会社ではなく株の発行会社に直接名義変更を申し出ます。
ただし非上場会社の株を相続するときには、評価額の算定が複雑であり相続税も高額になることが多いため、自分ひとりで手続きするのはかなり大変です。
被相続人の財産に非上場株式があるとわかったら、弁護士や税理士などの専門家へ早急に相談することをおすすめします。
まとめ

今回は株の名義変更について解説しました。
株の名義変更は、上場会社の株であればさほど難しい手続きではありません。しかし名義変更を怠るとさまざまなリスクがあります。
故人が生前に行っていた資産形成の努力を無駄にしないためにも、きちんと名義変更の手続きをしましょう。
 ライター紹介 | 杉田 Sugita
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。
受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。
▶︎今すぐ無料ダウンロード!



